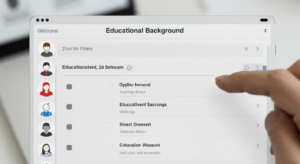1. はじめに
現代の職場では、「管理しない管理者」と「仕事しない社員」という二つの問題が組織の生産性や士気に大きな影響を与えています。これらの問題が同時に存在する場合、対応が難しくなり、組織全体のパフォーマンスが低下するリスクがあります。この問題が発生する原因を明確にし、それに対する具体的な解決策を講じることで、職場の健全な運営が可能となります。本記事では、このような状況において人事部が取るべきアプローチについて検討します。
2. 考察にあたって
管理者は、チーム全体をリードし、業務を円滑に進めるための役割を果たすべきですが、管理を怠ることで部下のモチベーションやパフォーマンスに悪影響を及ぼします。同時に、仕事をしない社員が存在すると、他のメンバーにも不満が広がり、職場の雰囲気が悪化します。これらの問題を放置すると、組織の効率と成果が大きく低下するため、場合によっては、人事部が適切に介入することが不可欠です。
3. 原因
3.1. 管理しない管理者が生まれる原因
管理しない管理者が生まれる理由は、モチベーションや心理的側面や適切な役割を認識していないなどの様々な理由がありますが、よく散見される3つの原因をピックアップしました。
原因➀過去の評価基準に固執
昇進する前は、個人の成果や業務効率が評価の基準となっていたため、それに固執することがあります。管理職になると、部下のパフォーマンスやチーム全体の成果が重視されますが、過去の成功体験にとらわれ、自分自身の業務だけに集中するケースが見られます。
原因②心理的なプレッシャーや不安
昇進によって新しい責任が増えることは、心理的なプレッシャーを感じさせる要因になります。特に、自分が管理職として期待に応えられるかという不安が強い場合、失敗を恐れて「慣れた仕事」に逃げ込む傾向があります。自分の専門領域に集中することで安心感を得ようとし、管理業務や部下の育成を後回しにしてしまうのです。
原因③昇進に対する自己満足
昇進のプロセスで昇進そのものが目標となり、昇進後の業務や役割に対するモチベーションが続かないこともあります。「昇進=ゴール」と考えてしまい、昇進後の新たな挑戦や責任に対する関心を失い、自己成長を図ろうとしない場合です。この場合、管理職としての責任感や意識が希薄になりがちです。
3.2. 仕事しない社員が生まれる原因
仕事をしない社員が生まれる原因は、そもそも本人のスタンスに問題がある場合もありますが、適切に管理されていないことによるモチベーション低下に起因する例も多いです。
原因➀モチベーションの低下
社員が、自分の意見が会社に聞き入れられないと感じたりすると、業務に対する意欲を失い、必要最低限の仕事しか行わないことがあります。職場でのフィードバックが不足していたり、キャリアの見通しが不明確である場合、社員のモチベーションが低下します。
特に、社員の会社の評価=上司への評価といっても過言ではありませんので、管理する上司が不在の場合やそれを放置する会社で働く意欲も低下します。
原因②スキルや能力の不足
社員が新しいプロジェクトで必要とされる技術スキルを持っておらず、業務を完了できないため、仕事に対する意欲を失ってしまいます。また、ICT知識が求められる現在、時代についていけず、アナログな方法でやってきた社員の意欲低下も近年よくあります。
十分なトレーニングや教育が提供されず、社員が必要な能力を持っていないことが原因となることがあります。
原因③明確な目標や指示の欠如
上司からの指示が曖昧で、社員が何を期待されているのか理解できず、結果的に業務を怠るようになることがあります。明確な業務目標や進捗確認が行われていないため、社員が何を優先すべきかを理解できず、仕事の優先順位を誤ってしまいます。
4. 人事部がとるべきアプローチ
4.1. 管理者へのアプローチ
➀過去の評価基準に固執への対応
●コーチングとメンタリングの提供
管理職としての転換がうまく進まない管理者に対して、経験豊富な管理者によるコーチングやメンタリングを行うことで、役割に対する理解を深め、チームマネジメントにシフトするサポートを提供します。例えば、ある新任管理者が自分の業務にのみ集中している場合、メンターとなるベテラン管理者が定期的に面談を行い、部下の育成やチームのパフォーマンスをどのようにマネジメントするかを具体的に指導したり、実際の成功事例を共有し、彼自身が新しい役割に自信を持てるようにすることが効果的です。
②心理的なプレッシャーや不安への対応
●心理的サポートの提供
管理職への昇進に伴うプレッシャーを軽減するために、メンタルヘルスケアやカウンセリングサービスを提供します。管理職に対するプレッシャーを軽減し、健全な心理状態を保てるようサポートすることが重要です。例えば、企業内でメンタルヘルスの専門家と連携し、管理職向けの「ストレスマネジメントセミナー」を開催します。そこでは、プレッシャーを適切にコントロールするための具体的な方法(例:マインドフルネス、タイムマネジメント)を学び、管理業務に自信を持てるよう支援します。近年、管理者に特化したカウンセリングサービスを導入する企業も少しずつ増えています。
③昇進に対する自己満足への対応
●フィードバックと報酬制度の強化
定期的なフィードバックと報酬制度を見直し、昇進後の管理者が継続的に評価され、成長を実感できるようにします。昇進が一度きりの報酬ではなく、努力に対する適切な評価と報酬があることを理解させます。例えば、人事部が四半期ごとに管理者のパフォーマンスレビューを行い、チーム全体の成果や部下の成長を反映した評価を行います。また、成果に基づくボーナスや昇進プログラムの一環として、優れた管理者には追加の報酬や表彰を行います。
4.2. 社員へのアプローチ
➀モチベーションの低下への対応
●社員の意見を取り入れる制度の強化
社員の声を反映するための仕組みを強化し、社員が自分の意見が反映されると感じられるようにします。例えば、人事部が「社員意見ボックス」や「定期的な社員アンケート」を実施し、社員の意見を収集したうえで、経営層にフィードバックします。透明性を持たせるため、改善された意見に対しては社内報や会議で発表し、社員にその効果がどのように反映されたかを明確にします。この透明性が、社員に自分の意見が尊重されていると感じさせ、モチベーションを向上させます。
②スキルや能力の不足への対応
●継続的なトレーニングとスキルアップの機会提供
社員が不足しているスキルを身につけられるよう、継続的なトレーニングプログラムを提供します。特に、ICTスキルやデジタルツールの活用に関する研修は、近年特に重要です。
人事部がオンライン学習プラットフォーム(UdemyやLinkedIn Learningなど)を導入し、社員が必要なスキルを自己ペースで学べる環境を提供します。例えば、ICTやデジタルスキルに関する必須コースを作成し、従業員全員が新しいスキルを習得できるようにサポートします。また、トレーニング終了後にはテストを実施し、学んだスキルの定着を確認します。
③明確な目標や指示の欠如への対応
●タスク管理ツールの導入
タスクの進捗状況や優先順位を可視化するために、タスク管理ツール(Trello、Asana、JIRAなど)を導入し、社員が自分の役割や目標を簡単に把握できるようにします。例えば、部署ごとにTrelloを導入させ、社員のタスクや進捗を視覚的に追跡できる環境を整備します。これにより、社員は自分がどのタスクに優先的に取り組むべきか明確に理解し、全体の目標に向かって計画的に業務を進められます。
5. 結論
「管理しない管理者」と「仕事しない社員」は、組織にとって深刻な問題ですが、原因を特定し適切なアプローチを講じることで改善が可能です。人事部は管理者と社員の双方に対してフィードバックやサポートを提供し、必要なトレーニングや業務調整を行うことで、職場全体の生産性を向上させることができます。組織全体の健全な運営を維持するために、問題に早期に対処し、改善を促す取り組みが重要です。